ぶちゅまるです。
どんな資格試験でもそうですが、
なるべく短時間で、勉強をして合格を狙いたいですよね。
一夜漬けを狙う多くの人は、
このようなことを考えているのではないのでしょうか。
- 勉強をできる限りしないで合格したい。(したくない)
- 気付けば試験日が近づいていた。
- 試験に対してやる気がない。
- 簡単な試験だし受かりそう。
ちなみに僕自身の勉強時間は1ヶ月で100時間でした。
その結果、試験を15分で解き終わり、
無事に合格しました。
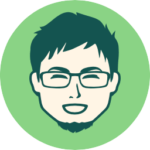
今思えば、明らかに過剰な勉強量でしたね。
絶対落ちたくなかったんでやりすぎました。笑
そこで、今回の記事は
消防設備士乙6は一夜漬けで受かることができるのか
についてまとめました。
どの試験でも一夜漬けはリスクがつきものです。
時間と受験料の価値は人それぞれですが、
無駄にはしたくないですよね。
果たして、一夜漬けで合格はできるのでしょうか。
それでは、どのようなポイントを
重視したら良いかみていきましょう。
そもそも一夜漬けで受かるの?
合格するのは非常に難しいです。
消防設備士乙6の試験範囲は
暗記内容がかなり多いです。
ただし、試験のポイントを押さえて
臨めば受かる可能性もあるかもしれません。
なぜなら、この試験は
過去問とほぼ同様の問題しか出ない
という点で対策がしやすいと言えます。
まずは、試験の内容について知りましょう。
試験内容について
試験は筆記分野と実技分野に分かれています。
ただし、どちらもマークシート形式の筆記試験ですので、
実際に実技を行うことはありません。
一部、記述式で問われるのでそこだけ注意が必要です。
一夜漬けで臨む為に、
試験科目と問題数について知っておきましょう。
具体的には以下に示します。
- 機械に関する基礎知識(5問)
- 消防関係法令(10問)
- 各類に共通する部分(6問)
- 6類に関する部分(4問)
- 構造機能および点検整備の方法(15問)
- 機械に関する部分(9問)
- 規格に関する部分(6問)
- 鑑別等(5問)
問題形式は4択のマークシートです。
答えは選択肢に必ずあるので、落ち着いて解きましょう。
試験時間は1時間45分あります。
頭に詰め込んだものを吐き出すには十分な時間です。
全問解き終わったら必ず見直しをしましょう。
一夜漬けの集中力は信用できません。
僕のおすすめは選択肢の正誤を問う部分に
アンダーラインを引いて確認することです。
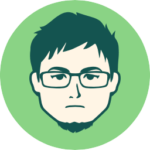
他の試験を夜勤明けで受験した時、
凡ミスの嵐で、危うく不合格になるところでした。笑
合格基準について
問題数の多いもので点数を稼ぎましょう。
足切りもあるので注意が必要です。
合格基準は以下に示します。
- 筆記試験
- 各科目で40%以上
- 全体60%以上
- 実技試験
- 60%以上
この基準からもわかるように、
全体の60%を取得する為には、
問題数の多い科目を重視した方が良いです。
問題数が特に多い科目を以下に示します。
- 消防関係法令(10問)
- 各類に共通する部分(6問)
- 6類に関する部分(4問)
- 構造機能および点検整備の方法(15問)
- 機械に関する部分(9問)
- 規格に関する部分(6問)
この部分で点数を稼げれば、
全体60%以上の基準に乗せやすいです。
ここで注意したいのは、
機械に関する基礎知識は5問しかないことです。
3問落とすと不合格になります。
この科目は基礎的な計算問題が多いですが、
一夜漬けの状態では、一気にハードルが上がります。
特に集中力を高めて臨みましょう。
おすすめの参考書とテキスト
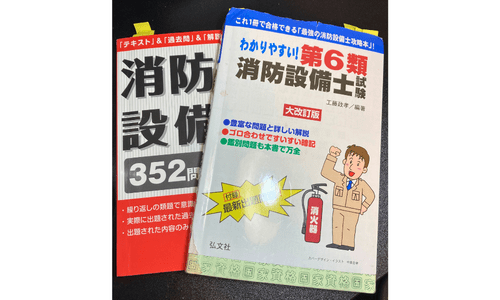
参考書は公論出版の消防設備士の過去問と弘文者の通称「工藤本」がおすすめです。
どちらも非常にわかりやすく、使い勝手がいいです。
過去問だけでも良いのですが、
両方ある方が合格の可能性は上がると思います。
勉強方法と重要なポイントについて
各科目の勉強方法と重要なポイントについて、
紹介していきます。
過去問や参考書を有効活用して、
最短ルートで合格しましょう。
勉強方法
暗記する内容が多いので、
インプットとアウトプットを同時にしていく必要があります。
ただし、過去問がほぼ変わらず出る内容がほとんどなので、
基本的には過去問を中心に暗記していきましょう。
問題の内容は90%以上が暗記だけで合格できてしまいます。
要するに、出題内容や問題さえ覚えれば合格できます。
暗記する際に、覚えにくい箇所などがあれば、
参考書を使って知識を補填していきましょう。
それでは、覚えにくい箇所や
暗記する際に重要なポイントをチェックしていきましょう。
重要なポイント
暗記する際に重要な項目をまとめました。
参考書などを使って確実に覚えましょう。
- 消防の組織
- 消防期間設置の義務:消防本部、消防署、消防団
- 火炎予防
- 消防長、消防署長、消防本部を置かない市町村長の権限について
- 消防の同意
- 消防同意の流れ:建築主⇔建築主事⇔消防長、消防署長、消防本部を置かない市町村長
一般建築物3日以内、その他7日以内
- 消防同意の流れ:建築主⇔建築主事⇔消防長、消防署長、消防本部を置かない市町村長
- 防火管理者が必要な条件
- 特定防火対象物:収容人員30人以上、非特定防火対象物:50人以上
要介護老人福祉施設等:10人以上 - 敷地内に二つ以上の防火対象物
- 不要な場合:準地下街、アーケード、山林、舟車(各条件あり)
- 業務内容について
- 特定防火対象物:収容人員30人以上、非特定防火対象物:50人以上
- 統括防火管理者が必要な条件
- 高層建築物31mを超えるもの
- 特定防火対象物;地階を除く階数3以上で収容人員30人以上
- 特定用途部分を含まない複合用途防火対象物
地階を除く回数が5以上で、収容人員が50人以上 - 準地下
- 地下街(消防長、消防署長指定)
- 業務内容について
- 防炎防火対象物
- 防炎対象物品
- 危険物施設
- 設置と変更→市町村長等の許可が必要
- 指定数量の10倍以上→警報設備の設置
- 消防の用に供する設備
- 消化設備、警報設備、避難設備
- 消防活動上必要な施設
- 無線、コンセント、排煙、連結散水、連結送水
- 消防用設備等の設置単位
- 開口部のない耐火構造の床または壁で区画されている場合
- 複合用途防火対象物の場合
- 特定防火対象物の地階で、地下街と一体(消防長、消防署長指定)
- 渡り廊下などで防火対象物を接続した場合
- 既存の防火対象物に対する基準法令の適用除外
- 消防設備等の届出と検査について
- 定期点検について
- 検定制度
- 総務大臣⇔申請者⇔日本消防検定協会等
- 検定対象品について
- 消防設備士制度
- 独占業務内容について
- 免状について
- 消火器の種類について
- 加圧式→ガス加圧、反応式
- 蓄圧式
- 運搬方法について
- 28kg以下→手提げ、据置、背負式
- 28~35kg以下→据置、背負、車載式
- 35kg以上→車載式
- 水消火器
- 強化液消火器
- 泡消火器
- 二酸化炭素消火器
- ハロン1301消火器
- 粉末消火器
- 住宅用消火器
- 能力単位
- 各消火器の充填量
- 各消化薬剤の性状
- 消火器の動作数
- 各消火器の操作方法
- 放射機能と使用温度範囲
- 自動車に設置する消火器
- 各部品の規格
- 消火器の鑑別
- 部品の名称
- 取り付けの基準
- 装着目的
- 装着する消火器の名称
- 部品の装着の必要性
- 装着時の注意事項
- 事象の説明
- 材質について
- 工具の使用目的、名称
まとめ
今回は消防設備士乙6は一夜漬けで受かることができるのかについてまとめました。
試験問題の内容がほぼ暗記なので、
一夜漬けで合格できないことはないと思いますが、
基本的にはしっかり勉強して臨みましょう!
せめて、勉強期間が1週間は欲しいところですね。
落ちてしまうと、時間と受験代が無駄になるので、
できる限り一発合格を目指しましょう!
ここまで読んでくださった方、お疲れ様です。
そして、ありがとうございます。
この記事が誰かの役に立っていたら嬉しいです。
それでは、今日もご安全に!
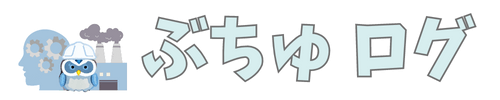
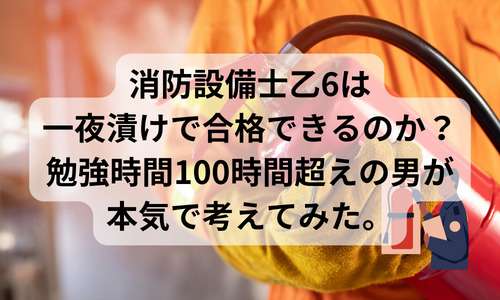


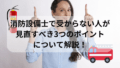
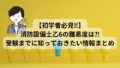
コメント